- 2025年5月5日
【初心者必見】ChatGPTで売れるステップメールを作る完全ガイド|プロンプト&成功事例付き
「ChatGPTを使えば、ステップメールも簡単に作れる」──そう聞いて試してみたものの、「結局どうプロンプトを書けばいい……

「ChatGPTやClaude、Geminiでセールスコピーが書けるって、本当に“売れる”のか?」
興味はあるけど、どこか半信半疑。
そう感じている方は、意外と多いんじゃないでしょうか。
実を言うと、私も最初は疑ってました。
でも今では、AIを使って20本以上のLPやウェビナー台本を制作し、累計300万円以上の売上を現実にしています。
もちろん、どのAIを使っても同じように成果が出るわけじゃありません。
結果を分けるのは、「どのAIを使うか?」よりも「どう使うか?」なんです。
特に、プロンプトの設計が売上に直結すると言っても過言じゃない。
今回は、私が実務で使い倒してきた主要なAIツール7種を徹底比較。
特に、ChatGPT・Claude・Geminiについては、それぞれの特徴と実践レビューをお届けします。
さらに、実際に成果を出した**“売れるプロンプト”の例**も公開します。
AIコピーで結果を出せるのか?
20年のマーケティング現場で培った知見と検証をもとに、腹落ちする答えをお届けします。
もしあなたが今、AIの導入を迷っているなら。
この記事が「自分に合ったAIの選び方」と「効果が出る使い方」のヒントになるはずです。
では、いきましょう。
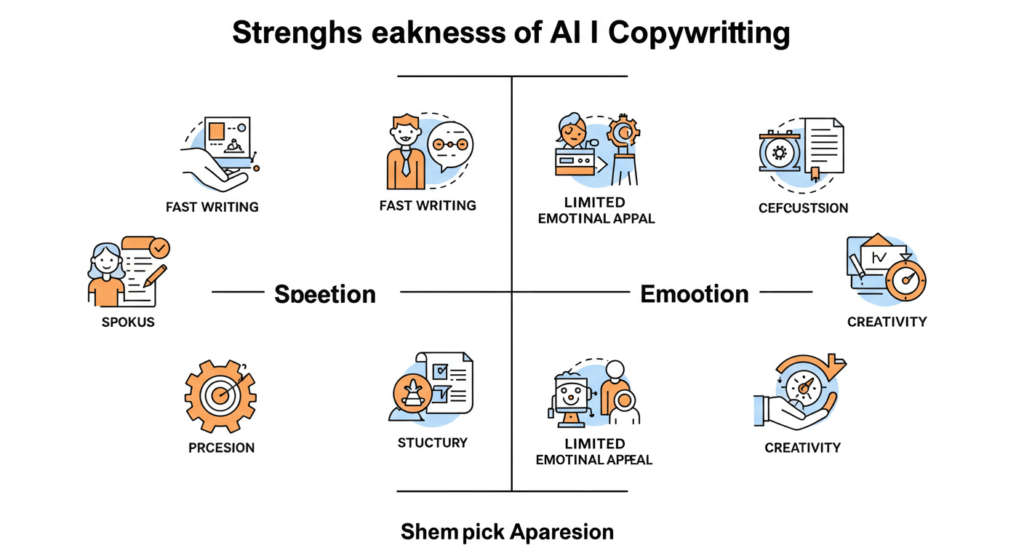
正直に言います。
AIに“全部任せておけば勝手に売れる”そんな時代は、まだ来ていません。
なぜか?
AIは確かに優秀です。
ChatGPTやClaudeなどを使えば、構成が整った読みやすい文章は一瞬で出てきます。
事前に指示をしっかり練れば、トーンの調整や文体の変化もある程度可能です。
でも、問題はそこじゃないんです。
「誰に向けて、どんな場面で、どの感情を揺さぶるか?」
この“戦略の芯”を握っていない限り、どんなに綺麗な文章が出てきても、売れません。
たとえば・・・
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| ○ | 文法的に正確で、整った文章を高速生成できる |
| ○ | 事前に指示を工夫すれば、多様なトーンで書ける |
| × | 感情の機微や読者の“引っかかり”を捉えるのは苦手 |
| × | 同じ指示でも毎回ブレやすく、成果の再現性に課題 |
私も実際に、「とりあえずAIに任せて書かせたコピー」では、ほぼ無反応でした。
でも、ターゲットの状況や葛藤に“グッと寄り添うプロンプト”を練ったことで、あるLPでは300万円超の売上を叩き出すことができました。
つまり、AIコピーはすでに「現場で使える武器」になっています。
でも、“誰でも簡単に成果が出る魔法のツール”ではありません。
大事なのは、
どこまでAIに任せて、どこから人間が関わるか?
そして、どんな視点で指示を出すか?
この視点があるかないかで、成果はまるで変わってきます。
次の章では、私が現場で使っている主要AIツールの違いと、それぞれのリアルな使用感をお伝えしていきます。
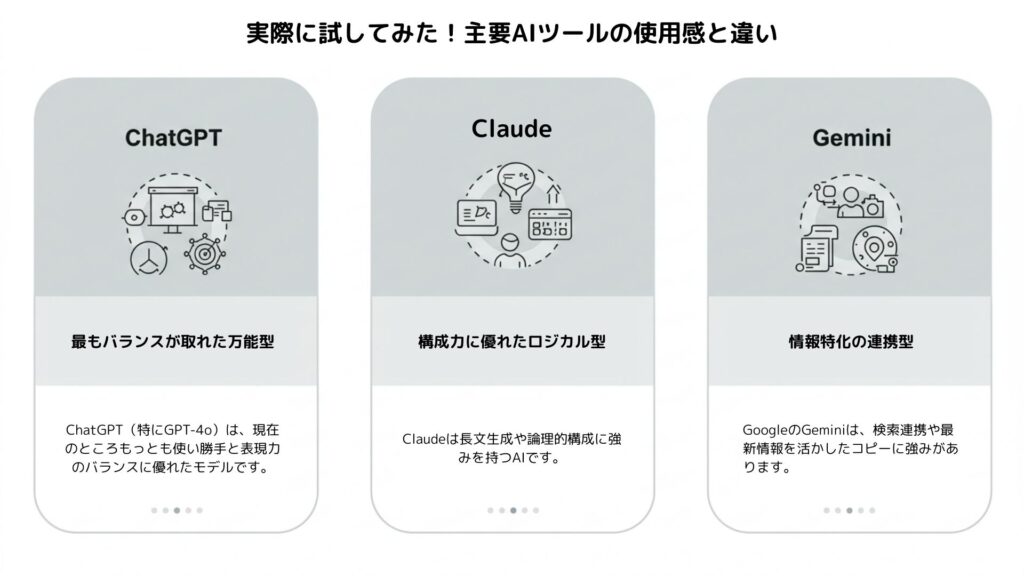
AIでセールスコピーを書くなら、「どのツールを選ぶか?」が成果を分けます。
実際、私が現場で試してきた中でも、使うAIによって反応率に差が出たことは何度もありました。
ここでは、私が実務で特によく使っているChatGPT・Claude・Geminiの3大モデルについて、特徴や使い勝手をリアルにまとめてみました。
まず結論から言うと迷ったらChatGPT(特にGPT-4o)を選んでおけば間違いないです。
私自身、このツールで作成したLPで300万円以上の売上を出したことがあります。
汎用性が高く、どんなジャンルの商材にも対応しやすいのが最大の強み。
コピー初心者~中級者の方には、まずChatGPTをおすすめします。
AIに慣れるにはちょうどいい、頼れる相棒です。
Claudeは、とにかく構成がうまい。
まるでロジカルな人間ライターが手書きしてるかのような、丁寧で筋道の通った文章を出してきます。
そのため、BtoB商材や高単価サービスのコピーで力を発揮します。
「ガチの構成で攻めたい」人向けです。
GoogleのGeminiは、検索連携や最新情報の扱いに優れた情報特化型AIです。
「新製品レビュー」や「比較記事」など、情報優先のコンテンツには使える場面も多いですが、
セールスコピーとしては、まだ細かい調整が必要だと感じました。
AIでセールスコピーを書くとき、**結果を左右する最大のポイントは「プロンプトの質」**です。
どんなに優秀なツールでも・・・
こちらの指示がふわっとしていたら、返ってくるコピーもぼんやりしたものになります。
たとえば、AIにこう頼んだことはありませんか?
「キャッチーなセールスコピーを作って」
……気持ちはわかります。
でも、これだけだとAIは判断材料がなさすぎて、「誰に向けて?」「どんな商品で?」「どういう場面で?」がまったく見えません。
その結果、**誰にも刺さらない“普通の文章”**が出てくることになります。
さらに厄介なのが、企業が配布している「テンプレプロンプト」をそのまま使うケースです。
一見、便利そうに見えますが・・・あれって、**自分の商品や状況に合わせて“カスタマイズするのが前提”**なんです。
そのまま流用すれば、当然ズレたコピーになる可能性も高くなります。
私が実務で300万円の売上を出したときに使ったプロンプトには、以下の3つの要素が必ず含まれていました。
この3点を明確にすればするほど、AIの出力は説得力と精度がグッと上がります。
さらに、AIの強みは「何度でもやり直せる」こと。
私も実際、売上300万円を出したプロンプトを作るまでに、10回以上は調整を繰り返しました。
ちょっとした表現の違いや、フォーマットの工夫で、反応率は驚くほど変わります。
「AIでコピーって、本当に大丈夫なの?」
よく聞かれる質問です。
確かに、AIコピーには強みもあれば、ハマると怖い“落とし穴”もあるのが事実。
ここでは、私自身の現場経験をもとに、AIコピーの「リアルな利点」と「見落としがちなリスク」を正直に整理しておきます。
AIは、万能な魔法の杖じゃありません。
だけど、使い方を間違えなければ、作業スピードも発想力も桁違いに跳ね上がる。
私自身、AIを“補助ツール”として使うことで、企画・構成・検証のサイクルが何倍も早くなりました。
すべてを任せてしまえば失敗します。
でも、人間の感性とAIの機能をうまく組み合わせれば、コピー制作はもっと楽に、もっと強くなる。
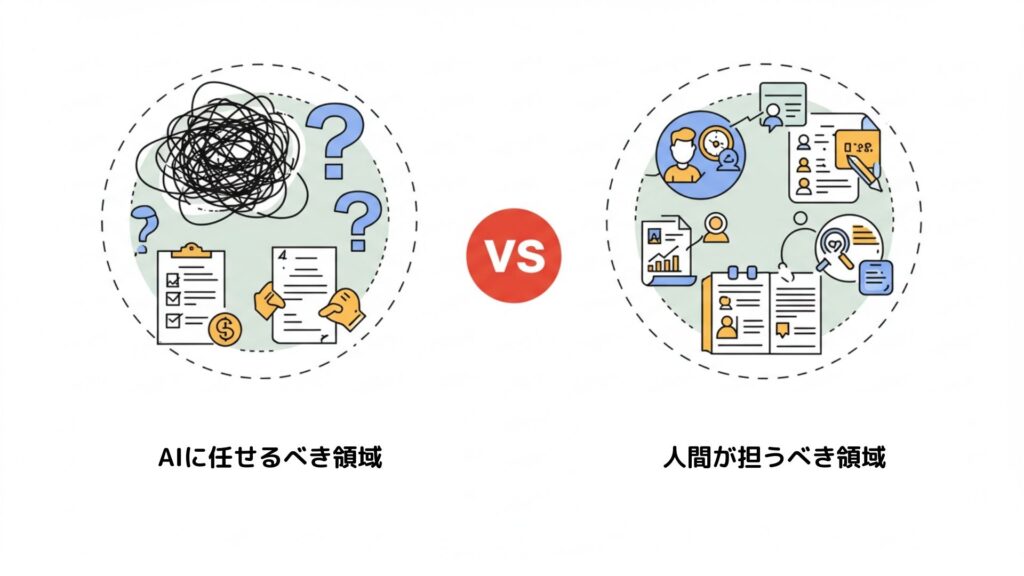
AIでコピーライティングを行ううえで、成果を出せる人と出せない人の違い。
それはたった一つ
「どこまでをAIに任せ、どこからを人間が担うか?」
をちゃんと分けているかどうか。
この見極めができるだけで、コピーの質も、スピードも、大きく変わります。
ここでは、私自身が実務でやっている**“AI×人間の役割分担フロー”**をリアルにご紹介します。
実際の現場では、私は次のような流れでAIを活用しています。
AIをただの“自動生成マシン”として扱うのではなく「チームの一員」として、適材適所で仕事を振る。
これが、AI時代のコピーライティングで成果を出すための、新しい“働き方”だと感じています。
もう、AIでセールスコピーを書くのは“実験”じゃない。
実務で成果を出すための、確実な“実用ツールになっています。
ただし、ここで大切なのは、「どのツールをどう使うか」をちゃんと理解し、場面ごとに使い分ける視点。
これがないと、せっかくの高機能も活かせません。
まず、具体的に見てみましょう。
大切なのは、AIに丸投げするのではなく、*プロンプト設計と人間の“仕上げ”**でしっかり“味付け”をすること。
私自身、実際にAIコピーで大きな成果を出せたのは、
「どのツールをどう使えば、誰にどんな言葉が届くのか」を常に意識していたから。
AIはあくまでツールに過ぎず、その力を最大限に引き出すのは、使い手であるあなたの理解と戦略です。
この記事が、あなたにとって**コピー制作の“新しい選択肢”**となり、初めの一歩を踏み出すきっかけになれば嬉しいです。
まずは、自分の商品やサービスに合ったAIをひとつ選び、プロンプトをじっくり工夫して試してみてください。
その一歩が、あなたの次なる成功へと繋がります。
どう思いますか?今すぐ、あなたも始めてみませんか?